
はまぐりと言えば、三重県の名産品である「桑名の焼きはまぐり」が有名です。
しかし、この美味しいはまぐりにも種類があり、さらに国産と中国産があります。
国産と中国産のはまぐりの違いも気になりますよね。
スーパーで手に入るはまぐりも、表示が国産でも中国産の可能性があるとのこと。
中国産だと危険なのか、チョウセンハマグリとハマグリの違いや貝類の種類の見分け方などを紹介します。
はまぐりの中国産は危険?安全性は大丈夫?

スーパーで手頃な価格で売られているはまぐりを見ると、
「中国産だけど食べても大丈夫?」
「国産と何が違うの?」
と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、中国産のはまぐりがすべて危険というわけではありません。
ただし、国産とは流通経路や種類が異なり、注意して見ておきたいポイントがあるのも事実です。
この章では、中国産はまぐりの安全性について、公的な情報をもとに分かりやすく整理します。
そのうえで、国産との違いや見分け方についても後半で詳しく解説していきます。
はまぐりの国産と中国産の違いは?
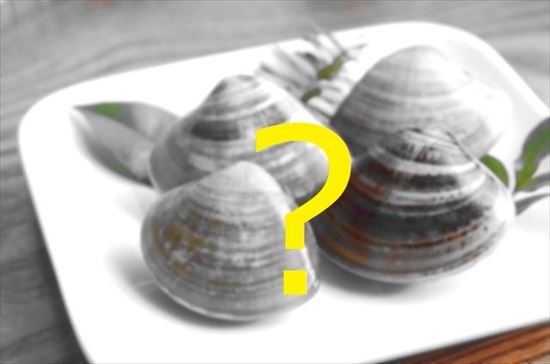
スーパーなどで流通しているはまぐりは、大きく分けて次の3種類があります。
- ハマグリ(地蛤):国産。三重県・桑名などが有名
- チョウセンハマグリ:国産。名前に「チョウセン」とありますが外国産ではありません
- シナハマグリ:中国産として流通することが多い種類
名前だけを見ると分かりにくいですが、現在スーパーで多く見かけるのは中国産の「シナハマグリ」です。
国産の「ハマグリ(地蛤)」は漁獲量が少なく価格も高いため、日常的に流通する量は限られています。
一方で「チョウセンハマグリ」は国産ではあるものの、見た目が異なるため混同されがちです。
※流通量と価格の違いから、日常的にスーパーで見かけるのは中国産が中心です。
| 比較項目 | 国産はまぐり | 中国産はまぐり |
|---|---|---|
| 流通量 | 少ない | 多い |
| 価格 | 高め | 比較的安い |
| 種類 | 2種類 | 主に1種類 |
| 見分け | 見た目だけでは難しい | 同左 |
実際、熊本大学の逸見泰久教授も
「ハマグリ類の形態的な違いは量的なものであり、初心者が形態だけで識別するのは難しい」
と述べています。
個体差も大きいため、素人が一目で国産か中国産かを見分けるのは簡単ではありません。
では、一般の消費者がスーパーでできる見分け方はあるのでしょうか。
次の章で、見た目や表示から判断する際のポイントを整理します。
中国産はまぐりの安全性|厚生労働省の検査結果
中国産のはまぐりについて、「危険ではないのか」と不安に感じる方も多いかもしれません。
現在、日本に輸入されるはまぐりを含む二枚貝については、
厚生労働省が残留物質や有害物質の検査を行っています。
公表されている検査結果を見る限り、近年の調査では、
はまぐりを含む二枚貝で健康への影響が懸念される事例は確認されていません。
このことから、中国産だからといって、直ちに危険な食品であるとは言い切れない状況です。
※検査結果の詳細は、厚生労働省が公表している資料で確認できます。
令和3年度の厚生労働省の中間報告の資料
→検査結果は10ページ目。
はまぐりの見分け方|国産か中国産か判断するポイント
はまぐりの国産・中国産を、見た目だけで正確に見分けるのは簡単ではありません。
専門家も指摘している通り、個体差が大きく、初心者が一目で判断するのは難しいのが実情です。
ただし、スーパーなどで購入する際に確認できるポイントはいくつかあります。
判断ポイント①表示を確認する
まず最も確実なのは、パッケージの産地表示を確認することです。
現在、日本で販売されているはまぐりには、
「国産」「中国産」などの原産国表示が義務付けられています。
見た目だけで判断せず、必ず表示をチェックしましょう。
判断ポイント②価格帯を見る
価格も一つの目安になります。
国産のはまぐりは漁獲量が少なく、価格が高めになる傾向があります。
一方、中国産のはまぐりは比較的手に取りやすい価格で販売されていることが多いです。
判断ポイント③ 見た目は参考程度に

殻の色や模様で判断しようとする方も多いですが、色味や模様には個体差があり、見た目だけでの判断はあくまで参考程度に考えましょう。
「黒っぽいから中国産」「白っぽいから国産」といった単純な見分け方は、誤解につながることがあります。
不安な場合は、産地表示がはっきりしている商品を選ぶことが、もっとも安心できる方法と言えるでしょう。
まとめ
中国産のはまぐりは「危険なのでは?」と不安に感じる方も多いですが、公的機関の検査結果を見る限り、近年は大きな問題が確認されていません。
一方で、国産のはまぐりは流通量が少なく、価格も高めになる傾向があります。
見た目だけで国産・中国産を正確に見分けるのは難しいため、購入時は産地表示を確認することが、もっとも確実な判断材料です。
不安な場合は、表示がはっきりした商品を選び、下処理や加熱調理を適切に行うことで、安心してはまぐりを楽しむことができるでしょう。
はまぐりを安全に美味しく食べるためには、産地の見分け方だけでなく、下処理や保存方法も重要です。

